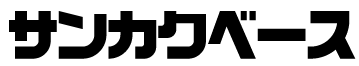二
この伏見城の土木へ日稼ひかせぎに来る労働者の数だけでも、千人に近かった。その多くは、新曲輪しんぐるわの石垣工事にかかっているのである。伏見町はそのせいで、急に、売女ばいたと馬蠅うまばえと物売りが殖ふえ、
「大御所様景気や」
と、徳川政策を謳歌した。
その上、
「もし戦争になれば」
と、町人たちは、機と利を察して、思惑に熱していた。社会事象のことごとくを、そろばん珠にのせて、
「儲もうけるのはここだ」
無言のうちに、商品は活溌にうごいた。その大部分が、軍需品であることはいうまでもない。
もう庶民の頭には、太閤時代の文化をなつかしむよりも、大御所政策の目さきのいい方へ心酔しかけていた。司権者は誰でもいいのである。自分たちの小さな慾望のうちで、生活の満足ができればそれで苦情がないのだ。
家康は、そういう愚民心理を、裏切らなかった。子どもへ菓子を撒まいてやるより易々いいたる問題であったろう。それも徳川家の金でするのではない。栄養過多な外様大名に課役させて、程よく、彼らの力をも減殺させながら効果を挙げてゆく。
そうした都市政策の一方、大御所政治は、農村に対しても、従来の放漫な切り取り徴発や、国持くにもちまかせを許さなかった。徳川式の封建政策をぽつぽつ布しきはじめていた。
それには、
(民をして政治を知らしむなかれ、政治にたよらせよ)
という主義から、
(百姓は、飢えぬほどにして、気ままもさせぬが、百姓への慈悲なり)
と、施政の方策をさずけて、徳川中心の永遠の計にかかっていた。
それはやがて、大名にも、町人にも、同じようにかかって来て、孫子の代まで、身うごきのならない手かせ足かせとなる封建統制の前提であったが、そういう百年先のことまでは、誰も考えなかった。いや、城普請しろぶしんの石揚げや石曳きに稼ぎに来ている労働者などは、明日あしたのことさえ、思っていないのである。
昼飯をたべれば、
「はやく晩になれ」
と祈るのが、いっぱいな慾念だった。
それでも時節がら、
「戦争になるか」
「なれば何日いつ頃?」
などと、時局談は、いっぱし熾さかんだったが、その心理には、
「戦争になったって、こちとらは、これ以上、悪くなりようがねえ」
という気持があるからで、ほんとにこの時局を憂うれいたり、平和の岐点をじっと案じて、どの方へ曲がるのが国と民のためだろうなどと考えているのでは決してないのである。
「――西瓜すいかいらんか」
いつも昼休みに来る百姓娘が、西瓜の籠を抱えて触れて来た。石の蔭で、銭ぜにの裏表を伏せて、博戯ばくちをしていた人足の群れで、二つ売れた。
「こちらの衆は、西瓜どうや。西瓜買うてくれなはらんか」
と、群れから群れへ唄ってくると、
「べら棒め、銭がねえや」
「ただなら食ってやる」
そんな声ばかりだった。
すると、たった一人ぽち、青白い顔をして、石と石のあいだに倚よりかかって膝を抱えていた石曳きの若い労働者が、
「西瓜か」
と、力のない眼をあげた。
痩せて――眼がくぼんで――日に焦やけて、すっかり変ってしまったが、その石曳いしひきは、本位田又八ほんいでんまたはちだった。